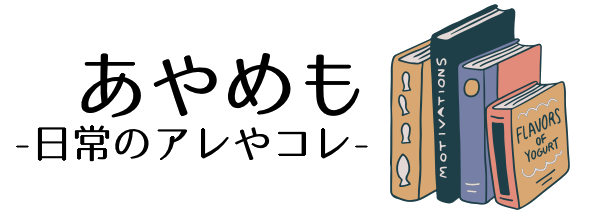「よく来なさった、気の済むまで滞在なさると良い。アルバ、宿に案内して差し上げなさい」
「はぁい……じゃなくてさ」
先ほどまでうつらうつらと船をこいでいたはずの村長は、思いの外はっきりした口調で話すとあっさりと男——セラータに滞在の許可をだしてしまった。
普段と変わらぬ村長の態度にうっかり流してしまいそうになったが、私の耳が聞き流してはいけない単語を拾った気がする。
「今サラッと流したけど、魔王って言わなかった?」
「言ったよ、息子だけど。ほらこれ、うちの紋章」
そう言って差し出されたのは剣の柄。
そこには魔王家の象徴である、剣に巻きついた蛇を三日月が囲っている紋章が刻まれていた。
この国では余程の田舎者か無知でない限り、この紋章を知らないことはないだろう。
何故なら教会や図書館など、領主の支援で運営している施設の何処かには、必ず紋章が刻まれているからだ。
それが目の前の男が持った剣に刻まれていた。
「…領主じゃん!」
魔王といえば国でも重鎮で、息子もこんな辺境ではまず見かけないような存在だ。
なにせこの村は領地の端っこである。驚きのあまりセラータを指差してしまった。
「そうだよ。でも領主は親父だし、次の代は上の兄貴の予定で俺が偉いわけじゃないって。だから楽しく冒険者やってるんだよ」
「放蕩息子の典型か…」
くだらないやり取りをしている横では、村長がニコニコしながらベンチに腰掛けている。
「とりあえず腹も減ったし、飯買いに行かせてよ」
「そうね、私も何か食べたいわ」
私たちは村長の家を出ると、先程通ってきた目抜き通りへと足を向けた。
そろそろ昼に差し掛かるためか、そこかしこからいい匂いが漂っている。
「アルバちゃんのおすすめは?」
「串焼き一択」
「男らしいな……」
私おすすめの串焼き屋へと向かっていると、商店街へ入った途端に周りがやけに騒がしくなった。
セラータは影からキャアキャア言ってるお姉様方に向かって、のんきに手を振っている。
それに便乗してか、果物屋のおばさんまでもが声をかけてきた。
「あんた!さっきのいい男じゃないの、うちで果物買って行っておくれよ!サービスするからさ」
みんな顔がいい男に甘すぎではないだろうか。
おばさんの恰幅の良い体の向こうでは、娘であるルーシーの姿が見えている。
彼女もノリノリで、普段はあまり付けない髪飾りまでつけているのが見えた。
「……ルーシー、串焼き何本食べる?」
「5本よろしく!」
ちょっとした意地悪のつもりで聞いてみたら、思いのほかゴツい答えが返ってきて、戸惑いを隠せない。
因みにルーシーは私の親友で、花より団子派である。
セラータへの興味は割とすぐに削がれたようで、串焼きを買い終わる頃には村には普段通りの様子が戻ってきていた。
店番を終えたルーシーを交え、私たちは3人で広場にあるベンチに腰掛けて串焼きを|貪《むさぼ》っている。
「意外とあっさりしてるのよねぇ…」
ぼそりとルーシーが言う。
「肉が?」
「お姉様方よ。肉は今関係ない」
両手に串焼き肉を持って主張されても説得力は皆無だ。
口の周りも心なしか脂でツヤツヤしているように見える。
「旅人とのロマンスなんて、こんな辺境じゃ現実味がなさすぎるわよ。だからルーシーだって冗談半分のおめかしだったんでしょ」
「そうよ、夢見るのも楽じゃないもの。やっぱりエルムの街が限界かな」
|件《くだん》の旅人を挟む形で座りながら、夢のない話をするルーシーと私。
真ん中では複雑そうな表情で、セラータが黙々と肉を食べている。
田舎の恋愛事情は結構シビアだ。
村よりは広いが、街へ出ても誰某の付いたや別れたなどと言う話は3日と経たずに広まっていく。
それでもこの環境を甘んじて受け入れるのは、遠くの街へ旅立つのも簡単な事ではないからだ。
「アルバ、いつか村を出て行くんでしょう?」
「……どうかな」
ルーシーの言う通り、いつかは行きたいと思っている。
けれど決心は未だにつかないのだった。
***
「さて!腹ごしらえもしたし、私は店に戻るね。セラータさんはこれから宿に?」
「そ、アルバちゃんに案内してもらう予定」
「それならいい部屋交渉してもらうと良いよ!アルバは宿の女将さんと仲良いから」
じゃあねと手を振って小走りになる背中は、振り向くことはなかった。
肉を食べる間、それなりに打ち解けたらしいルーシーとセラータだったが、彼らの間にも現実が邪魔をしてロマンスはうまれそうにないらしい。
二人でルーシーを見送ると、食べ終えた串を片付けて宿に向かうことにした。
「ね、アルバちゃん。この村ってどんなところなの?」
「どんなって……見たままよ。すぐ側に山があるし、村だか森だか分からないから魔物もよく来るの」
隣の村へ行くだけで結界や農園、牧場といった存在が充実している。
しかしほぼ森と呼べそうなこの村は自生の果物があるため農園がなく、獣が多いせいで牧場や家畜は基本飼えない。
そのせいで肉は獣を狩るか買ってくるしか無く、畑も小さなものくらいしかできないのだった。
「ルーシーも臨時で自警団として補助するくらいはできるし、小さいやつ相手ならその辺の子供でも殴り倒してるわよ」
「そんなに?俺てっきり結界で平和なもんだと思ってたけど」
「結界も年に二度くらいは起動するけど、獣がすぐに壊しちゃうから……かえって危険だって敢えて直してないの」
魔物とは基本的に、体内に魔石を有するもののことを指している。
ダンジョンなどの|瘴気《しょうき》が濃い場所から|生《しょう》じる存在の他に、獣が瘴気を取込んで変質してしまった場合などもあるらしい。
そう言った魔のものは基本的に、街などの周りに設置された結界装置によって弾かれる。
しかし獣は普通に出入りできてしまうため、ただでさえ村の囲いがザルなこの村では、あまり結界が意味を成さないのだ。
なのでこの村の夜は、自警団の巡回がある事が普通になっている。
そのせいか、結界装置が起動した日は朝までお祭り騒ぎだ。数日くらいしか保たないけれど。
「そのおかげと言うべきか、自警団はそれなりに屈強なはずよ」
「だろうね。俺も結構強いはずなんだけど、一発貰っちゃったし」
「あら、わざとじゃなかったの?」
「油断してたのは事実だけど、避けられなかったよ」
笑いながら尋ねるとセラータは肩をすくめ、おどけた様子で|宣《のたま》うのだった。
***
商店街を挟んで広場とは反対側に行くと、目的の宿屋が見えてきた。
赤い屋根の大きめの建物には、宿を表す看板が下がっている。
「ここがこの村唯一の宿『かやの葉亭』よ」
ドアを開けるとドアベルが揺れて涼やかな音が響いた。
その音でカウンターの奥から、女将さんが顔を出すのが見える。
「先輩、お客さんひとり連れて来ました」
「いらっしゃい!村長から聞いてるよ」
張りのある声で出迎えてくれた彼女は元々、自警団の一員として活躍していた先輩だ。
女性にしては恵まれた体格に加え筋肉質なので、少々威圧感はあるが細かなところにも気を配れる、優しい人である。
「一泊30ユール、食事付きは追加で10ユール。7日分以上まとめてだと少し安くするよ」
「助かる。とりあえず7日、食事付きで頼めるか?」
「はいよ。250ユールだよ」
宿帳をカウンターの下から取り出し、先輩は説明を続ける。
「うちは小さいから、いい部屋って言ってもたかが知れてるけれど……角にある一番日当たりの良い部屋を用意しといたからね」
セラータが代金を支払い部屋の鍵を受け取るのを確認すると、私は手を振って|踵《きびす》を返した。
「じゃあ、私は村の|警邏《けいら》に戻るわ。何もないところだけど楽しんで行ってね」
「ん、ありがと」
見回りが終わったら屋台でクレープでも買おう。
そう思って宿を出ようとしたのだが、丁度駆け込んできたきた乱入者によってそれは叶わなくなってしまった。
「アルバ!小規模だが魔物の群れだ、空からくるぞ!」
なんなんだ、ゆっくりスイーツも食べられないじゃないか。