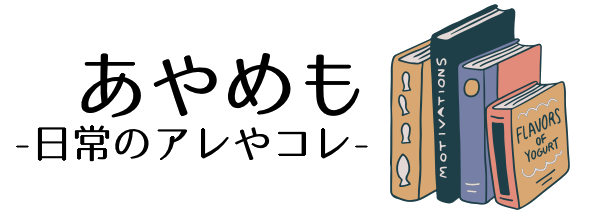窓の向こうが夜の|帳《とばり》に沈む頃、アルバの家ではいつもより豪華な食卓が準備されていた。
椅子が一脚追加され、客人であるセラータは私の横で、両親と和やかに談笑している。
急だったため一頭分ではないが、それなりの量を追加された肉が並んでいるさまは圧巻だ。
普段はあまり出てこない酒も、木箱ごと部屋の隅に控えている。
「へぇ、じゃあアルベルトさんとシルバさんも冒険者やってたんだ」
「そうなのよぉ。たまたま臨時で組んだパーティだったんだけど、なんだか気が合っちゃって」
程よい照りの肉と一緒に並ぶ野菜は、|瑞々《みずみず》しさから新鮮なものであることが伺える。
少量取り分けて口に運ぶと、シャキシャキとした歯ごたえと共に自然な甘みが堪能できた。
そうして私がひとり食事を楽しんでいる横では、相変わらず聞き飽きた両親の馴れ初めなどが語られている。
父さんも母さんも、これでは客人を接待しているのか、客人に接待されているのか分かりやしない。
「そのまま組んでA級までは昇級できたが、シルバが怪我をするのも嫌だったんでな。あの頃は今より平和で……楽しくはあったが、プロポーズを機に引退したんだ」
「あら、あなたったら」
いつまで経っても熱々な両親は、お客人の前でも通常運転のようだ。
嫌な顔ひとつせず、質問したりニコニコしながら聞いて|相槌《あいづち》を打つセラータは、話を聞くということに相当慣れているらしい。
そんな様子をぼんやり眺めていると、不意にセラータがこちらを向いて問いかけてきた。
「アルバちゃんが自警団に入ったきっかけは?」
私にまで話しかけてくるとは思って居らず、驚いて言葉に詰まってしまう。
いや、そもそも入ったきっかけに大した理由がなかったからかも知れない。
「……両親が腕っぷし強くて自警団に所属してたから、当然ながら自分も入るものだと思って修行した結果、かな」
「あらぁ、勉強が嫌いだからでしょ?」
母の鋭いツッコミはこの際聞かなかったことにする。
だがきっかけと言われて思い当たるのは、この村の状況や両親との日課の修行、冒険者への|漠然《ばくぜん》とした憧れの延長のようなものくらいだった。
あれ、本当に大した理由じゃなくない?
「冒険者になりたかったからじゃないんだね」
セラータはルーシーと私の会話を覚えていたらしい。
落ち着いた声は別に咎めているわけでもないのに、なぜか私の心を焦らせる。
「憧れてはいるけど、村も好きだから大事にしてるのよ」
返す言葉はどこか、言い訳めいたものだった。
憧れから先に進めずにいるのは、元冒険者だった両親の手前なんだか気まずい。
けれど故郷を出て行くにはまだ決心がつかないのだ。
そんな私の様子を見かねてなのか、父さんが問いかけてきた。
「アルバ。お前がよく旅人の世話焼いてたのは何のためだ?」
父さんは普段、私のやることにあまり口を出してこない。
そんな父に言われるほどとは、我ながら情けない話である。
「自警団としてもあるけど……旅の話とかも、いろいろ聞きたかったから」
「無理に村で生きて行く必要は無いんだぞ」
そう言いながらも父さんの表情は少し寂し気だ。
普段はどちらかというと厳しいが、やはり一人娘である私のことは可愛いらしい。
防犯上の理由で言えば、見知らぬ旅人をそのまま村に入れるのは、あまり良いとは言えないのだ。
なので見知らぬ相手には誰かが声をかけるけれど、私がよく案内しているのも事実。
それに私が冒険者に憧れているのは、隠しているわけでも無いため、村の皆が知っているのだ。
父の許しも今得られ、残るは私の意思だけなのである。
それなのに、私が決心するにはまだ何かが足りないらしい。
無意識に母へ視線を|遣《や》ると、こちらを見ていたらしい母さんと目が合った。
「……懐かしいわね。私は魔法の研究ついでにダンジョンに潜ってたら、いつの間にか冒険者やってたのよ」
「えっ初耳なんだけど」
微笑む母さんは、なんでも無いことのように言う。
普段はおっとりしているが、意外と行動派のようだ。
そういえば昔、「学園は遠いし通うお金がないから、自己流で勉強と資金稼ぎをした」とかなんとか言っていた気がする。
「俺は孤児院から出るためだったが、とりあえず村の働き口がぱっとしないから街まで出てみようって程度だったぞ」
父さんが語るきっかけも、相当適当なものだった。
結局いいのが無くて気がついたら冒険者になってたがな、と父さんは笑う。
気がついたらなっていたという二人が両親である。
それなら娘の私が、冒険者に憧れているからなったというのは、正当な理由かも知れない。
なってみたい、けど。
「……もうちょっと、考えてみるよ」
まだ少し、この愛しい時間を惜しみたいのだ。
***
豪華な夕食を終え酒も程よく回ってきた頃、アルバとセラータはようやく上機嫌な両親から開放された。
|湯浴《ゆあ》みは食事前に済ませているので、あとはもう眠るだけである。
とはいえ自室はセラータが使う事になっているし、今夜からしばらくの寝床になるソファはリビングのもの。
今はキッチンに両親がいるので、まだ|静寂《せいじゃく》とは程遠い状態だった。
「今日は疲れたでしょ。ベッド小さいから落ちないように休んでね」
「借りられるだけでもありがたいよ。壊れたら直すから安心して」
冗談混じりに言葉を交わす。
移動や戦闘はともかく、宿が壊れて民家で接待だなんて私なら気疲れしてしまうだろう。
二階の廊下でセラータとわかれると、とりあえず酒が回って火照った体を冷ますため、廊下の窓から屋根へとよじ登る。
真ん中辺りまで歩くと、落ちないように座って屋根に背を預けた。
「冒険者には、なりたいんだけどなぁ……」
食事の時のやり取りを思い出し、ポツリと呟く。
明日も晴れるのか、広がる星空はとても澄んでいる。
「なればいいじゃん」
「うわっ!?」
独り言に返答があったとき以上に驚くことは無いと思う。
声のした方を見遣ると、先程わかれたばかりのセラータが屋根に登ってくるところだった。
「よっ、さっきぶり」
「よっじゃないわよ。聞いてたの?」
「聞こえたのー」
しれっと隣に腰を下ろすセラータは、私が睨んでもお構いなしだ。
おそらく登った時に、思った以上に足音などが伝わってしまったのだろう。
別に聞かれて困る事でもない。
ため息をひとつ付くと、相変わらず眩しいほどに明るい夜空を見上げた。
そんな私にわざとだろうか、セラータは先程の言葉をもう一度繰り返す。
「なればいいじゃん、冒険者」
いつまでも決断出来ずにいる私に、呆れているのだろうか。
責める視線を覚悟して目を向けるが、セラータは私と同様に空を見上げて居るだけだった。
「簡単に言うわね」
「そんなつもりはないけどさ」
けど、なんだろう。
続きの言葉が気になって、無言のまま聞く姿勢を見せる。
そんな私の心情を察したのか、セラータはちらりとこちらを見遣ると、すぐに空へと視線を戻して言葉を続けた。
「アルバちゃん、冒険者になりたいんでしょ」
「そうね、いつかはと思ってる」
「それだけ強けりゃ、冒険者としてもかなり上に行けるはずだよ。人族なら尚更、体が動く早い内がいい」
そういえば、セラータは魔族だ。
彼らの寿命は長い。
個体差はあるが、時には数百年を超える者も居るという。
セラータからすれば、人族だからこそ、迷うよりは動けと言いたいのかも知れない。
たとえそれが、ほんの一時関わるだけの相手だとしても。
「多少腕に自信はあるわ。だけど野盗でも出たらどうするの?私みたいな小娘、集団で来られたら一発でおしまいよ」
「だからって諦めるのは勿体ないと思わないか?今生きてるのはアルバちゃん自身なんだから、『いつか』なんて考えない方が良いよ」
「……お気楽ね。一度きりだから、慎重になるのよ」
「そうかな」
あと一歩決めきれず、迷い続ける私の背を押したいのだろう。
セラータの後押しは無責任に思えるほどに積極的だ。
むしろ、一時しか関わらないと思って言ってるのでは無いか、と思えるほどに。
両親や友人たちの元から離れる事を憂い、手が届く程近くにある冒険者の存在に戸惑い、|躊躇《ちゅうちょ》する私。
どちらかを選べば、もう一方が消えてしまいそうな気がする。
そんな何年も引きずってきたはずの迷いは、唐突に打ち砕かれることになった。
セラータの、たった一言によって。
「俺はワクワクするね」
こいつ、今なんて?
一瞬、何を言われたのかわからなかった。
だって私がずっと失くすことを恐れて、選べずにいたことだったから。
「わ……ワクワク?」
「うん、考えてみなよ。俺は魔王の、キミは勇者の子孫なんだから」
「そうよ、だから?」
「だから、俺と一緒に旅に出ようよ、アルバ」
問い返すと、セラータは一拍置いてとんでもないことを宣った。
驚いて振り向くと、言葉の通りに琥珀の瞳を輝かせた横顔が見える。
「共に戦った魔王と勇者として、2人で歴史に名前を残そうよ」
なんてことを考えるのだろう、この男は。
しかしとても魅力的な話に思えてしまい、私は思わず頷いたのだった。